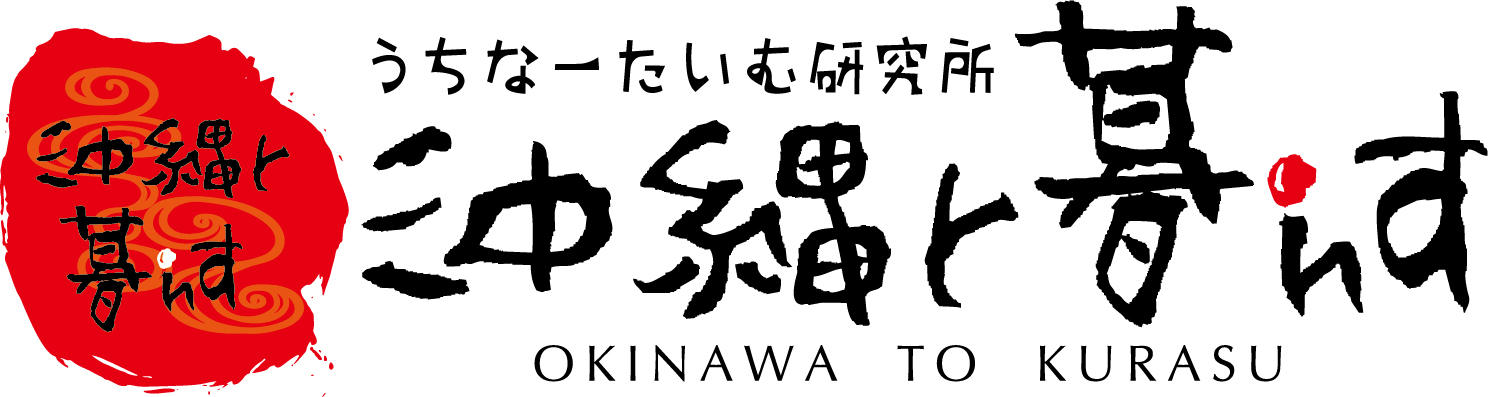「あぁ、また沖縄に行きたいなぁ」と考える時に思い出すのは、沖縄旅行で食べたうちなーごはん(沖縄の家庭料理)がおいしい居酒屋さん?、それとも青い空や言葉にできないほどキレイな海ですか。
そんな時でも大丈夫です。
ちゅら海にはすぐに入れなくても、あのおいしいうちなーごはんは、ポイントさえおさえれば、自宅でもかなりおいしく再現することができるんです。自力で沖縄の家庭料理がおいしく作れるようになれれば、「あぁ、また沖縄に行きたいなぁ」と思う回数が減るだけでなく、「なんかもう沖縄にいる気分」が味わえるというもの。
昔ながらの沖縄料理が長寿を支えていたのがよくわかるのは、塩分や脂肪分を減らす工夫があり、何よりヘルシーなこと。その調理方法も合理的です。
いくつかのポイントやうちなーごはんの基本をまとめましたので、ぜひ最後までご覧になって、実際に作って食べてみてくださいね。
さぁ、それでは早速コツを紹介していきましょうね〜♬
目次
料理のコツ:まずは、これだけは押さえよう!
本当においしい沖縄の家庭料理を食べたことがある人なら、ひとくち食べて思ったはずだ。なんだろう、このおいしさ?とっても上品で、思ったよりしょっぱくも脂っこくない、ああ「だしが濃い」のかも。実はヘルシー?
ピンポーン!全部、正解です。
本土の料理と比べて、沖縄の家庭料理は複数のだしを上手に組み合わせて使うので、おいしいのですね。
特筆すべきは、豚だし。豚肉料理の調理の過程で出るだしを、濃いめにとったかつおだしと合わせることで、コクを出します。だしが濃いので塩分が控えめにできるのも特徴です。
沖縄家庭料理のおいしさを作る3種のだし
❶かつおだし

まずは、かつおだし。
鰹節の消費量は、沖縄県が日本一!というのを知っている人は意外と少ない?
スーパーでは鰹節コーナーがババーンと大きな棚一面作られていて、うちなーんちゅ(沖縄の人)の鰹節愛がわかります。
かつおだしは本土でもおなじみですが、なんと沖縄でだしをとるときに使う鰹節の量は、約2倍!!とにかくだしが濃いです。
沖縄でも鰹節はだしをとって捨ててしまうので、沖縄県中のだしがらを集めたら、肥料とか燃料になるんじゃないの?と思ったり。
1つ目のポイント。
鰹だしをとる時には、鰹節をいつもの2倍の量で!!
ケチらず豪快に入れることで、うちなーごはんをおいしくします。
❷豚だし

沖縄では、豚肉は三枚肉(皮付きの豚ばらブロック)が一般的。軽くゆで、表面の血や臭みをとってから、約1時間半ほど下ゆでするのがポイント。この時に、アクと脂をていねいに取り除いたゆで汁が、豚だしになります。
下ゆでした豚肉の方は、さらに煮汁で煮込んでラフテーなどを作ります。個人的には、ゆでたてのアチコーコー(あつあつ)をスライスして、わさび醤油でいただくのも好み^^
この下ゆで、手間がかかる作業なのだけれど、この豚だしが料理入ると一気にうちなーごはんモードマックスに!!やっぱり必要なんです。休みの日や時間のある時に、大量に作ってしまうのがおすすめです。
はい、それでは2つ目のポイント。
ここ⇩、テストに出ます!
本当においしいうちなーごはんを食べたいなら、
「下ゆでした豚肉」と「豚だし」を常備しよう!!
常備が無理でも、三枚肉やソーキ(豚スペアリブ)を下ゆでした汁は、アクと脂を取り除いてとっておこう!←ここ重要^^
豚だしとうまく付き合うための補足情報
*スーパーで多めにゲット
皮付きの豚ばらブロック肉は、本土ではなかなか手に入りませんが、スーパーの精肉コーナーで「豚ばらブロックを2キロください」と予約しておくと普通に用意してくれるので、ぜひ試してみて。
*たくさん作って保存
<豚だし>
豚だしはペットボトルなどに入れ冷蔵庫で数日はもちます。使いきれない時には、製氷皿に入れて凍らせたものを、ビニールに入れて冷凍しておくと使いたい時に使いたい分量だけ取り出せて便利。いつもの料理の時や、市販のそばだしにプラスしても、ぐっとコクが出ておいしい。
<下ゆでした三枚肉>
下ゆでした豚肉も、使いたい大きさに切り分けて冷凍しておけば、チャンプルーやジューシーにいつでもインできて便利。ポーク(スパムランチョンミート)のチャンプルーもよく見かけますが、やっぱり豚肉入りのチャンプルーがおいしい。
さらに、補足情報。
なんでこんなに面倒な作業をするの?というと、沖縄在来の豚肉には脂が多かったので、カロリーを減らすため。ミネラルやビタミン、コラーゲンなどは閉じ込めつつ、脂肪分は減らす合理的な調理法といえます。そして、元々は冷蔵庫のなかった時代の保存の知恵でもありました。より長持ちさせるために、塩をまぶして放置してから下ゆでするスーチカーという料理もあります。
❸昆布(だし)

こちらも、本土でおなじみの昆布!沖縄県がずっと消費量日本一だったのは、平成63年ごろの話。平成8年まではベスト5に名を連ねていたのをご存知でしょうか。でも、県内で入手できるほとんどは、北海道産。キリッ
昆布が採れない沖縄で、なぜこれほどに愛されたのかというと、江戸時代に盛んだった北前船が、昆布を蝦夷地(北海道)から運んできたから。その航路は、日本海沿岸、瀬戸内海を経由して、大阪、薩摩(鹿児島)、琉球(沖縄)へ。沖縄から清国(中国)へも相当量が輸出され、清の生糸や反物、漢方薬の材料などと取引されていたそう。
この航路、「昆布ロード」と呼ばれ、日本の食文化を一変させたそう。ちなみに、2017年時点の消費量1位は、京都。長く1位を独走してきた富山県を抜いたようです。(富山に何があった!?)
長くなりましたが、本土ではだしをとって捨ててしまう昆布。
沖縄では、料理に入れてそのまま食べます!だしをとるものではなく、そのだしを生かしつつ捨てずに食べる、立派な食材です。なのでかっこで(だし)としました。体に良いものを無駄なく取り入れるという、うちなー精神を感じますね。
定番のクーブイリチー(昆布の炒め煮)はその代表選手といえます。
どうして沖縄の昆布消費量が1位じゃなくなっちゃったかというと、うちなーごはんの昆布料理は、乾物の状態から水で戻し、屏風だたみにして包丁で細く切り、さらにそれなりの時間をかけて煮込むor炒め煮にするという、調理の作業に時間がかかるから、今どきの沖縄の主婦には敬遠されたのでしょう。少し寂しい気もしますが、沖縄のスーパーで細切り昆布を見かけるとお土産に買って帰る自分もいるので、やはり現代人は料理に時間をかけなくなっているのでしょうね。
3つ目のポイントは、昆布!
そのまま食材として使って、だしも活用しつつ、そのまま食べる。
この「沖縄家庭料理のおいしさを作る3種のだし」の3つのポイントを押さえることで、自宅で作るうちなーごはんが格別においしくなること、間違いなし。
このほかに、干し椎茸の戻し汁なんかもよく使います。だし出まくりです。
さらに、お家に居ながらにして沖縄が味わえる工夫をいくつか^^
おいしいものを食べたときの合言葉
私が、沖縄料理研究家の先生の料理を初めて食べて、そのおいしさに感動し、興奮しながら地元居酒屋の店主に話すとこう教えてくれました。
沖縄の人はおいしいものを食べたときには、こう言うんですよ。
「あー、ぬちぐすいやっさー。」
ぬちぐすいとは、うちなーぐち(沖縄の方言)。そのまま訳すと、ぬち(命の)ぐすい(薬)となる。
「めっちゃおいしー!!命の薬だぁ。」という意味ですかと聞いてみると、
こんな答えが返ってきた。
「のーりー、ぬちぐすいっていうのはね、食べ物だけじゃないんですよ。良い音楽を聴いて心地いいのは、みみ(耳)ぐすい。美しい海や空を見て目の保養になるのは、みー(目)ぐすい。その感動の最上級が、ぬちぐすいなんですよ。そうそう、人に優しくされた時にも使いますね。」
それを聞いて・・・思わず、すご!!!
もとい、なんておおらかなで素敵な考え方なのだろうと。
おいしく体に良い食べ物を食べて自分の体の栄養になったり、素晴らしい体験で心が癒されたりしたこと、つまり体が喜ぶ経験をした時に使う言葉だということなのだとか。
このほかに、「ごちそうさまでした」のうちなーぐちも教えてもらった。
「くすいなびたん(体の薬になりました)」
沖縄では、体に良いものを食べて病気にならない体を作る「医食同源」の考え方が根付いていたからできた言葉とか。
そのほかにも、「くわっちーさびたん」という言い方も。くわっちーはごちそうという意味。いただきますは「くわっちーさびら」。
どちらも若い人はあまり使わなくなっているそうなので、お店のおばあに伝えたら喜ばれるかも!?
さて、自分でおいしいうちなーごはんを作ってしまって、感動したら一言つぶやいてみよう。そうすれば、もうあなたは「沖縄と暮らす」というライフスタイルが身に付き始めている証拠(笑)。
家庭料理の本当のおいしさの秘密
基本の3種のだしをマスターした、うちなーぐちもマスター!?
これでもうあなたは、一歩うちなーごはんの達人への階段を登り始めました。
そこでもうひとつ。
うちなーごはんがよりおいしくなる、この言葉。
沖縄のお母さんが作ったおいしい料理を絶賛した時に、お母さんがにっこり笑って恥ずかしそうに返してくれたりする、言葉です。
「てぃーあんだ が入っていたのかねぇ。」
てぃーあんだは、直訳するとてぃー(手の)、あんだ(脂)。
お料理に手の油が染み込むくらい丹念に、手塩にかけて作った愛情たっぷりの料理というような意味になる。さーたーあんだぎーのあんだと一緒ですね!アンダギーを作るときには、本当に手に油をつけて記事を丸めるんですよ。ちなみに、さーたーは砂糖。
話がずれましたが、少し手間ひまがかかっても、家族の笑顔が見たくてお母さんは頑張っちゃうんですね。もちろん簡単に作れる料理の時にも、おいしい魔法をかけましょう。
てぃーあんだ、で。
東京で沖縄家庭料理教室に通うなら
いやー、基本はわかったけど、どうも自己流でこれで大丈夫なのかわからない。
1回だけでいいから、沖縄の先生に習いたいなぁと思っている方。
そうですね、百聞は一見にしかず。
うちなーたいむ研究所の同僚、くーみーは都内の自宅で少人数制の沖縄料理教室を定期的に開催していますので、ぜひチェックしてみてくださいね!
沖縄の料理研究家の先生のところに20年間通ったのーりーも、お墨付き。
くーみーのおいしいうちなーごはんが、1回から体験できますよ。
(調理の講習と実習・レシピ・ゆんたく・ビール付き!?)
くーみーは海外でも出張お料理教室をしたりしていますので、
東京じゃないけど、うちの近くにも来てー!と言うリクエストがあれば、
飛んで来てくれるかも?コメントお待ちしています^^
くーみーのお料理教室については、こちらの記事もチェック!