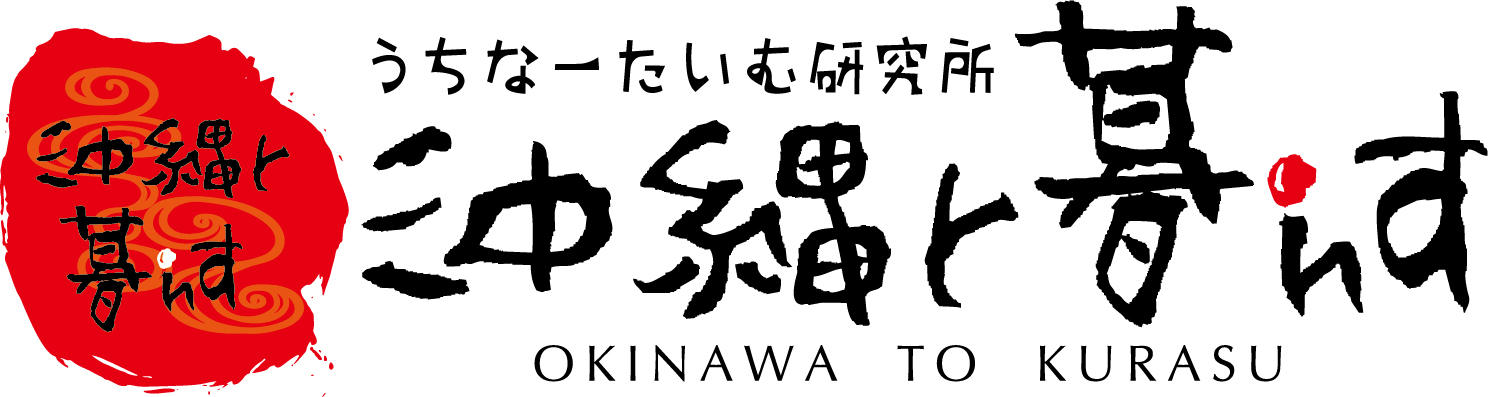- 泡盛をお土産でもらったんだけど、何となく開ける気にならないんだよね
(嫌いなわけではないのだけど、飲まずに眠ったまま・・・) - 「おうち飲み」をいつもと違う雰囲気で楽しみたい
- お酒は好きだけれど、カロリーが気になる
なんていうことをボヤボヤ〜っと考えている方には特に、ぜひとも読んでいただきたい記事です。
泡盛に馴染みがある方にもそうでない方にも、「コーヒー泡盛」の美味しさや作る楽しみをお届けできれば・・・という思いで書いていきます。
目次
コーヒー泡盛って何?
簡単な説明を
「泡盛コーヒー」とも言われますが、要は泡盛とコーヒーを組み合わせて飲むことです。
10年ほど前から沖縄で人気が高まっている泡盛の飲み方の一つで、老舗泡盛メーカーが泡盛コーヒーリキュールを発売したのがきっかけと言われていますが、今では大手コンビニエンスストアでも泡盛コーヒーのオリジナル商品を販売するほど、人気が定着しています。(沖縄県内にて発売)
飲食店によっては、自家製で作っているお店もあります。
なぜコーヒー味にして飲むの?
ズバリ、「美味しいから」です!そしてカラダにも優しめです。
泡盛はロック・水割り・ソーダ割り・お湯割りなど多様な飲み方ができるお酒であり、更には色々なフレーバーとも相性が良い(良い意味でフレーバーに染まりやすい)お酒でもあります。
中でもコーヒーとの相性は良く、泡盛の香りとコーヒーのアロマが組み合わさり、「大人のコーヒー」を楽しむことができるのです。
また、泡盛は糖質ゼロ・プリン体ゼロ!
ビールやワインといった醸造酒に比べてカロリーが低めであり、お酒を飲むことの罪悪感も少しは減るのではないでしょうか。
コーヒー泡盛の作り方
作り方は大きく2つ
- 泡盛をコーヒーで割る 「泡盛のコーヒー割り」
- 泡盛にコーヒー豆を漬ける
泡盛のコーヒー割りは、市販のアイスコーヒーを使えば一番カンタンに作れて、直ぐに飲めるというメリットがあります。(泡盛とコーヒーの割合はお好みで)
豆を漬ける方法ですと、最低1週間程度は時間を要します。
ですが、
・ 好きな豆を選んで、好みの味に仕上げられる
・ 日を追うごとに色合いや香りが変わってきて、ちょっとした「育てる楽しさ」を味わえる
といったメリットを重視し、コーヒー豆を泡盛に漬ける方の作り方をオススメしたいと思います。
作り方
材料

- 泡盛(30度程度のもの)・・・600ml
- コーヒー豆(酸味の少ない深煎りタイプがオススメ)・・・40〜50g
- 黒糖・・・お好みの量(目安:20〜30g程度、入れなくても良い)
準備
- 耐熱容器を煮沸するなどして殺菌し、乾かしておく
作り方
- 準備した容器に、全ての材料を入れる
- 陽の当たらない場所に置き、1日に1回 軽く揺らす
- 2週間程度経ったら、豆を取り出して完成!
(1週間を過ぎたあたりから飲めます)

豆は上部に浮いています
(下に沈んでいるのは黒糖です)
色づき始め、豆が少しずつ沈み始めます 
ほとんどの豆が沈み、
コーヒーの香りが強くなってきます
黒糖も溶け、黒褐色の泡盛コーヒーに!
飲めるようになるまで、もう一息!
ポイント
- 豆を浸けっぱなしにしておくと、豆の油分が浮いてきたり酸味が出過ぎることがありますので、できれば2週間程度経ったら取り除く方が良いでしょう。
- 飲み頃になったら冷蔵庫で保管し、早めにお召し上がりください。

泡盛をコーヒーで割って作るものとの大きな違いは、言うまでもなく「度数の高さ」です。
つまり、飲み方注意です!!
ですが、度数が高い分、アレンジ方法も多彩なのが魅力で、ロックや水割りで飲むほか、牛乳や豆乳で割ってカフェ・オ・レ風にしても美味しいですし、アイスクリームに掛けていただくのも大人スイーツとしてオススメです。
まとめ & カラダをいたわる泡盛豆知識
泡盛+コーヒーで飲むことの良さ、伝わりましたでしょうか?
- 泡盛はコーヒーの風味や香りとの相性が良い
- つまり、「泡盛は得意ではない」「泡盛を飲む機会が少ないので飲み方がよくわからない」と思っている方でも美味しく飲めるお酒になる
- 手軽に漬けて育てて、おうち飲みを楽しく
- 泡盛は糖質ゼロ・プリン体ゼロ!カロリーも抑えめの嬉しいお酒
最後にカラダをいたわる泡盛豆知識を。
泡盛や本格焼酎に含まれる香気成分には、血栓溶解を促す酵素(t-PA)やウロキナーゼ(u-PA)の分泌を促す成分が含まれていることがわかってきました。
つまり、固まった血を溶かして血液をサラサラにする健康効果が期待できるというわけです。
適量を守れば、お酒もカラダの味方に。
特にお湯割りは効果的で、お酒がお湯で温められると香気成分が香りやすく、内臓からの吸収を良くしてくれると言われています。
ちなみに「適量」とは、25度のお酒なら120ml程度です。(*)
・・・と、自分自身に言い聞かせながらクロージングとしたいと思います。
(*)適量とは体格などによる個人差があります
【参考資料】
「本格焼酎・泡盛スタイルブック」(日本酒造組合中央会発行)